脱炭素経営の目的と進め方、
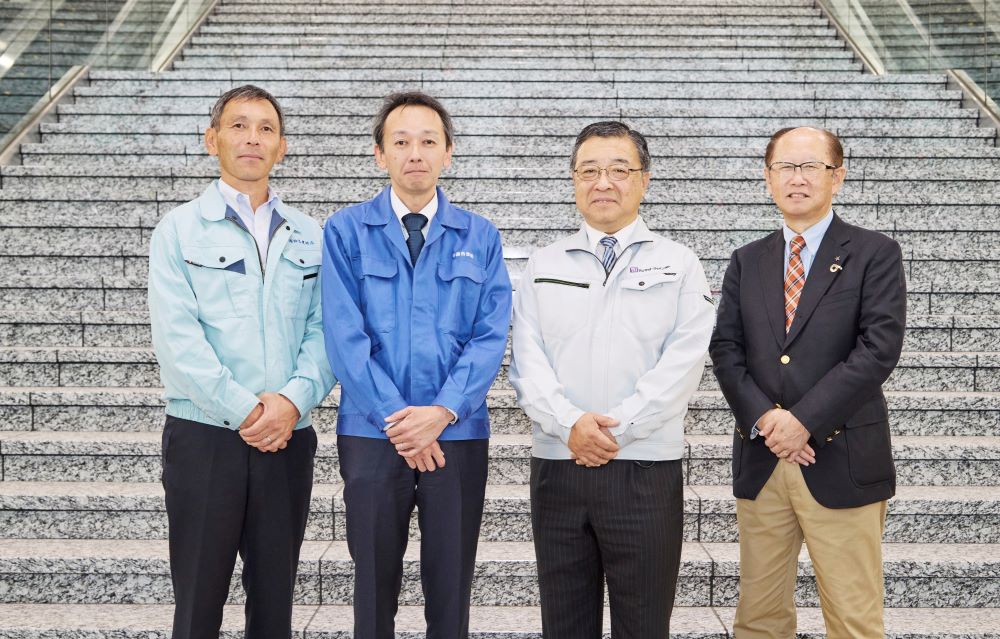
脱炭素経営の目的と進め方、IT企業、製造業、土木建築業ではどう違う?
株式会社きらぼしコンサルティング シニアコンサルタント 橋本斉氏(右端)
テレネットジャパン株式会社 常務取締役 佐々木良氏(右から2番目)
中島合金株式会社 代表取締役社長 中島一郎氏(右から3番目)
有限会社鈴木建材店 代表取締役 鈴木徳光氏(右から4番目)
脱炭素経営が未来をひらく 中小企業のための成長戦略
2025年10月22日、脱炭素経営に取り組む中小企業3社をパネリストに迎えて、「脱炭素経営が未来をひらく 中小企業のための成長戦略」と題したパネルディスカッション形式のオンラインセミナーが開催されました。参加いただいた3社の業種は、情報ネットワークの工事・保守サービス業、非鉄金属の鋳造・機械加工業、土木・建築業と三者三様。業界ごとの課題や取組の違いにもフォーカスして、現場のリアルな声をレポートします。
橋本氏による基調講演
セミナーは、ファシリテーターを務める株式会社きらぼしコンサルティングのシニアコンサルタント橋本斉氏の基調講演でスタート。きらぼしコンサルティングは、東京きらぼしフィナンシャルグループの子会社として、コンサルティングや経営情報の提供、セミナー、講演会などを通じて企業の成長支援を行っています。「補助金・融資をフル活用する 脱炭素経営の実現」と題した橋本氏の基調講演では、金融系コンサルタントとしての知見から補助金・助成金、金融サービスの活用ポイントについてお話がありました。

補助金や助成金探しに役立つ情報源として、中小企業基盤整備機構の支援サービス「SDGs・CNに対応したい」や、環境省が発信する情報サイトからは「脱炭素ポータル」を紹介。なかでも「脱炭素ポータル」は、カーボンニュートラルの基本情報、最新情報はもちろん、脱炭素経営の取組方法や補助・委託事業を網羅した中小企業向けの情報が充実していて必見とのこと。
補助金や助成金の相談をする際の準備としては「自社の削減計画を作ると同時に、計画に取り組むにあたり、人、物、金、時間、情報はあるのか、不足する物は何か、考えておくことも大切」と語ります。全国金融機関の環境問題に対する融資を一覧できる「全国銀行ecoマップ」や、東京都中小企業振興公社の「ハンズオン支援」なども紹介され、国や東京都、金融機関など多方面から情報を得る大切さを実感しました。
パネリスト3社様のご紹介
ディスカッションに先立ち、まずはパネリスト3社の代表から自社の紹介が行われ、各社の事業概要と脱炭素の取組についてお話いただきました。
■テレネットジャパン株式会社 常務取締役 佐々木良氏
インターネット等の通信ネットワークの工事、運用サービスをプロフェッショナル品質で届けるテレネットジャパンは、1990年、東京都北区に設立。2019年からはSDGsに力を入れ、社員は意識改革をめざす「身近にできる10のSDGs行動」カードを携帯、全社一丸となってサステナブルな社会の実現に取り組んでいます。脱炭素の取組としては、照明のLED化や情報システムのクラウド化、ピーク電力の削減と夜間電力の有効利用など、できることを積み重ねて電力削減の具体策を実施。
2023年には東京都から取組を評価され、HTT取組推進宣言企業の優良取組企業に選出されました。今後も取組を加速して、2040年までにカーボンニュートラル実現を目指しています。

■中島合金株式会社 代表取締役社長 中島一郎氏
中島合金株式会社は、1920年に東京都荒川区で創業。鋳造業として100年を超える老舗企業で、銅、銅合金、アルミニウム合金など非鉄金属に特化した鋳造技術を提供しています。約40年前に製造部門を茨城県つくば市へ移転したのを機に規模を拡大。現在は製造から機械加工まで幅広く対応し、鋳造業の「コンビニをめざす」と語るのは、5代目社長の中島一郎氏。
ガス溶解炉の炎で高温となる作業環境改善のため、20年ほど前に電気炉を導入。同時に電力を制御するEMSを設置し、増えた消費電力を低減する策も講じました。最近の取組としては、補助金を活用して工場屋根に太陽光パネルを設置。創電、省エネの両面から、消費電力の削減に取り組んでいます。

■有限会社鈴木建材店 代表取締役 鈴木徳光氏
50年前、ダンプ一台で創業した鈴木建材店は、建設現場で発生した残土を目利きし、畑や花壇の土として農家や植木屋に収めることから事業をスタート。これが縁で、公園や堤防造成の工事、家屋の解体などの土木工事へと事業が繋がり、一級建築士である現社長への代替わりを機に、現在は住宅の新築・リフォーム工事から店舗の設計、古材、古ガラスなど建築資材の販売まで、幅広い事業を手掛けています。
住宅設計ではエネファーム導入の推進をきっかけに、ZEH住宅、低炭素住宅を手掛けるようになり、脱炭素ビジネスの展開も進めています。自社の取組としては2020年に蓄電池を、2022年には電気自動車を導入し、2023年に江戸川区SDGs推進事業所賞を受賞。取組により一層の力を入れています。

各社の取組について詳しく紹介した記事がありますので、ぜひご覧ください。
・テレネットジャパン株式会社の記事はこちら
・中島合金株式会社の記事はこちら
・有限会社鈴木建材店の記事はこちら
パネルディスカッション
パネルディスカッションは以下5つのテーマに沿って、ファシリテーターの橋本氏の進行で行われました。
パネルディスカッションテーマ
1. そもそも脱炭素経営に取り組むきっかけは何だったのか?
2. 社内でどのような取組や進め方をしているのか?
3. 取り組む上でご苦労されたことは?
4. ご経験から、これから進める方へのヒントは?
5.今後の展望について
取組を始めたきっかけ、社内の進め方は?
①のテーマ「取組のきっかけ」については、各社とも当初は脱炭素への意識が強かったわけではありません。テレネットジャパンは電気料金の高騰を受け、省エネ対策として取り組みを始めました。中島合金は、50度近い過酷な作業環境の改善が主な目的でした。鈴木建材店は、創業以来の「もったいない精神」を背景にエネファームを導入したことがきっかけです。ファシリテーターの橋本氏は、「日本企業はもともと省エネに積極的で、皆さんのように当たり前に取り組んでいる企業も多いですが、実はそれが脱炭素の取組にあたるのです」と話します。
②のテーマでは社内における取組の進め方が話題となりましたが、その方法は業種によって違いがあるようです。テレネットジャパンが属するIT業界では、製造業のように直接的な燃料消費は少ないものの、通信インフラに係る電量消費の増大や環境負荷が課題。消費電力の高いオンプレミスシステムのクラウド化や照明器具のLED化などの設備更新とともに、こまめな消灯やクールビズ・ウォームビズの推進など、社員一人ひとりの行動を積み重ねて取組を進めています。
一方、物作りに燃料を使うしかない中島合金の場合は、従業員に対しては電気やガスの使用量を減らす指示はせず、EMSを設置することでシステムによる省エネの仕組みづくりを行ってきました。「高温で過酷な作業環境ですから、従業員が製造に専念できる環境を整えつつ、その裏で省エネの環境づくりを心掛けています」と、中島氏は語ります。中島合金の取組はSDGsにおける人権の分野にもあたり、脱炭素の取組が社会課題の複層的な解決に繋がる好例といえるでしょう。
太陽光発電の導入。事務所で活用するケースは?
脱炭素経営で気になるテーマに太陽光発電がありますが、業界によって経営課題が異なることから、導入の目的や活用方法に違いが見られました。今年から事務所と作業場に太陽光パネルと蓄電池を設置した鈴木建材店では、電力の自産自消で電気代の85%を削減できたそうです。
「これまでは少しの暑さは我慢して省エネを心がけていましたが、今年の夏は自家発電の電気を十分に使い、涼しい環境で仕事ができました。また、蓄電池の導入はBCP(事業継続計画)対策にも繋がり、台風で停電した時は復旧までの1時間を自家発電と蓄電池の電力を使うことで、業務を継続することができました。災害時の備えとして非常に有効だと実感しています」と、鈴木氏は話します。

製造業の太陽光発電導入には発想の工夫を
鈴木建材店のように、事務所等における利用であれば太陽光発電の費用対効果は十分といえそうですが、膨大な電力を必要とする中島合金のような製造業の場合はどうなのか。2年前、つくば市の工場に太陽光発電を導入した中島合金では、工場で使う電力の約5%を発電。
「なぜそんな中途半端な導入をするか」と問われることもあるそうですが、「溶解炉は非常に多くの電力を消費するため、それを賄うにはギガソーラ級の太陽光が必要になり、費用対効果が全く合わないのです。当社が太陽光をのせた目的は、5%の削減で浮いた費用で大型エアコンを導入し、工場内の作業環境を改善することにありました。作業環境をよくすることで生産効率が上がり、最終的に製造にかかる電気代も減ると考えています」と、中島氏は説明します。
売上規模に見合った投資金額に抑えるため、費用が嵩む蓄電設備導入を省いたことも、製造コストを下げるための判断の一つでした。中島合金の事例は、鋳造業に限らず、エネルギー消費量の多い製造業全般の参考になるでしょう。費用対効果を念頭に置きつつ、事業全体を俯瞰した活路の工夫が重要と言えそうです。
テナント企業は脱炭素をどう進める?
東京都ではテナントビルに本社を構える中小企業も多く、建物の所有者と利用者が異なることから、高効率空調への更新や照明のLED化など、取組を加速するうえでの課題にもなっています。そうした背景があるなか、テナント企業として脱炭素化をうまく進めているのがテレネットジャパンのケースでした。
同社は昨年の8月を転換点として消費電力の大幅削減に成功。テナント企業としてどのような障壁を乗り越えたのか、佐々木氏は語ります。「テナントビルの場合、設備更新を行うにはビルオーナーの了承を得る必要があります。当社はオフィス内照明のLED化を行い、1フロアのエアコンを最新型に更新いたしましたが、これもオーナーとの良好な関係があればこそといえます。ビルの設備ではありませんが、毎朝、小型ソーラーパネルを屋上に設置してポータブル電源に充電していますが、これもオーナーの理解を得て行っています。最近ではビル設備についてオーナー側からの提案もあり、積極的にコミュニケーションを図ることで信頼関係の構築に努めています」。ビルオーナーの対策や要請にも積極的に協力することで、ビル全体の取組として脱炭素化を進めるのもポイントといえそうです。
パネルディスカッションのふりかえり
今回のパネルディスカッションでは、業種の異なる3社がそれぞれの視点で取組を進めている点が印象的でした。ファシリテーターを務めた橋本氏はこう振り返ります。

「基調講演では補助金や助成金、融資の活用についてお話しましたが、窓口でご相談される際には、取組の方向性や目標を明確にしておくことが重要です。今回、参加企業の皆様からお話を伺うことで、脱炭素経営の実践には明確な目的と行動指針が不可欠であると、改めて実感いたしました。活動を進めるにあたり、投資規模に応じて国や自治体の補助金を使い分け、東京都の伴走支援やHTT実践推進ナビゲーター事業など専門家の支援もうまく活用していたことも参考になるでしょう。脱炭素経営を始めるにあたっては、カーボンニュートラルについて「知る」、CO2排出量を「測る」、目標や方針を「決める」、計画を「進める」というステップが大切です。わからないことがあっても迷う必要はありません。東京都はさまざまな支援策がありますので、まずは公的支援の窓口を訪ねて、脱炭素経営の第一歩を踏み出してください」
公的支援の窓口は多様にあり、どこを訪ねればいいのかわからない、という方も多いかもしれません。HTT実践推進ナビゲーター事業では、経験豊富なナビゲーターが企業ごとに最適な支援策をご案内します。まずはお気軽にお問合せください。(ご相談は無料です)
【前のページに戻る】

