経営の考えを現場へ、社内の取組を社外へ、

経営の考えを現場へ、社内の取組を社外へ、脱炭素の活動を繋いで広める
合同会社桑島技術士事務所 代表社員
桑島 哲哉(くわしま てつや)氏
中小企業のための脱炭素スタートアップ
自らを“脱炭素経営と現場の翻訳者”と称し、エネルギー課題の解決と環境に配慮した経営戦略の支援活動を行っている桑島哲哉さん。「中小企業のための脱炭素スタートアップ」と題したセミナーの内容を振り返りながら、社内における脱炭素の進め方についてお話を伺います。
Q1. 桑島様は、エネルギー視点による企業の環境経営支援がご専門と伺っています。これまでのキャリアや日頃の活動内容についてお話いただけますか。

半導体、電子部品のメーカーで設計や開発に従事しておりましたが、2007年からは環境部門の配属となり、社内の省エネ推進や再エネ導入、海外イニシアチブへの対応にも携わってまいりました。環境部門の責任者として活動した17年の間に、経営と現場の間にある意識のギャップを埋めることの大切さを実感し、両者を繋ぐ“翻訳者”となることに努めました。在職時のこうした経験を活かし、中小企業の皆さまにも経営と現場を繋ぐお手伝いができるのではと考え、退職後に合同会社を設立。経営と現場のエネルギー問題を繋ぐ“翻訳者”として、脱炭素の取組を支援しております。
Q2. 国内における脱炭素の動きをどう見ていますか。中小企業への影響についてもお聞かせください。

東京都の動きを見ますと、2030年のカーボンハーフに向け、CO2排出量削減活動に対する補助金や入札のアドバンテージなど、積極的な支援を展開しています。その結果、東京都の温室効果ガス排出量がどのように変化したかというと、現時点で私が把握している2022年の排出量は5,945万t、減少率は2000年比でわずか4.4%に留まっております。大企業の多くは取組を加速していますが、それだけでは目標達成が困難であることの表れといえそうです。つまり、中小企業も含めた全ての企業が取り組む必要があるということなのです。そうした背景もあり、取引先企業から排出量の算定や取組への要請がきている中小企業もあるのではないかと思われます。昨今ではSBT※1認定を取得する企業が急増していて、2023年3月から2024年3月の1年間だけで新たに479社が認定を取得、認定企業数は904社に上ります。SBT認定をした企業はサプライチェーンの企業に要請を出すことになりますから、ここ数年で中小企業の取組にもかなり大きな変化がでてくると思います。
※1 SBT Science Based Targetsの略。パリ協定が求める気候変動対策の水準と整合した温室効果ガス排出削減目標のこと。
参考 TCFD、CDP、SBT、RE100 カーボンニュートラルのイニシアチブ、どこがどう違う?
Q3. 中小企業が脱炭素を始めるには、なにを、どこから始めればよいでしょうか。
脱炭素を始めるにあたっては目標設定をされると思いますが、おおまかに長期、中期、短期と三層構造にすると進めやすいと思います。まず長期目標については、カーボンニュートラルといったスローガン的になる傾向にあり、短期目標については毎年の実績やコストを調べる実務になるかと思います。私は、その長期と短期をつなぐ中期目標というのが重要だと考えております。単に時間軸における中間地点であるだけではなく、それとは別の視点で、社内と社外の整合をとり、結びつける役割が求められます。そのためには、社内の活動を社外に明示できるよう、明確な目標設定をすることが大切です。例えば、取引先や金融機関から要請があったときに、どう対応すればいいのか迷うこともあろうかと思います。そうしたときもSBTのような信頼ある目標を設定していると、対応がスムーズになります。
Q4. SBTについては、他社の排出を算定するScope3で悩む声も多く聞かれます。
Scope1、2のみを対象とする中小企業版のSBTを利用する手もあります。中小企業版とはいえ、SBTi※2が運営しておりますので、脱炭素の取組を明示する有効な手段であるといえます。ただし、Scope1、2という自社排出だけで年4.2%削減することになる点には留意が必要です。例えば、事業拡大すれば排出量は増えていくわけですから、増えた分も余計に減らしていかないといけませんので、再エネやバイオマス燃料の導入なども合わせて検討する必要もあるかと思います。逆にScope3まで組み込んだ方が、事業活動の上流、下流まで対策の幅を広げられるメリットもあります。コミットにはそれなりの覚悟が必要だと思いますが、目標達成できなくてもペナルティはありませんので、まずはコミットして取組をアピールするというのも手です。とはいえ結果はSBTiのホームページで公表されますので、自社の評価や信用を維持するためにも実現に向けた道筋をきちんと立てることが肝要です。
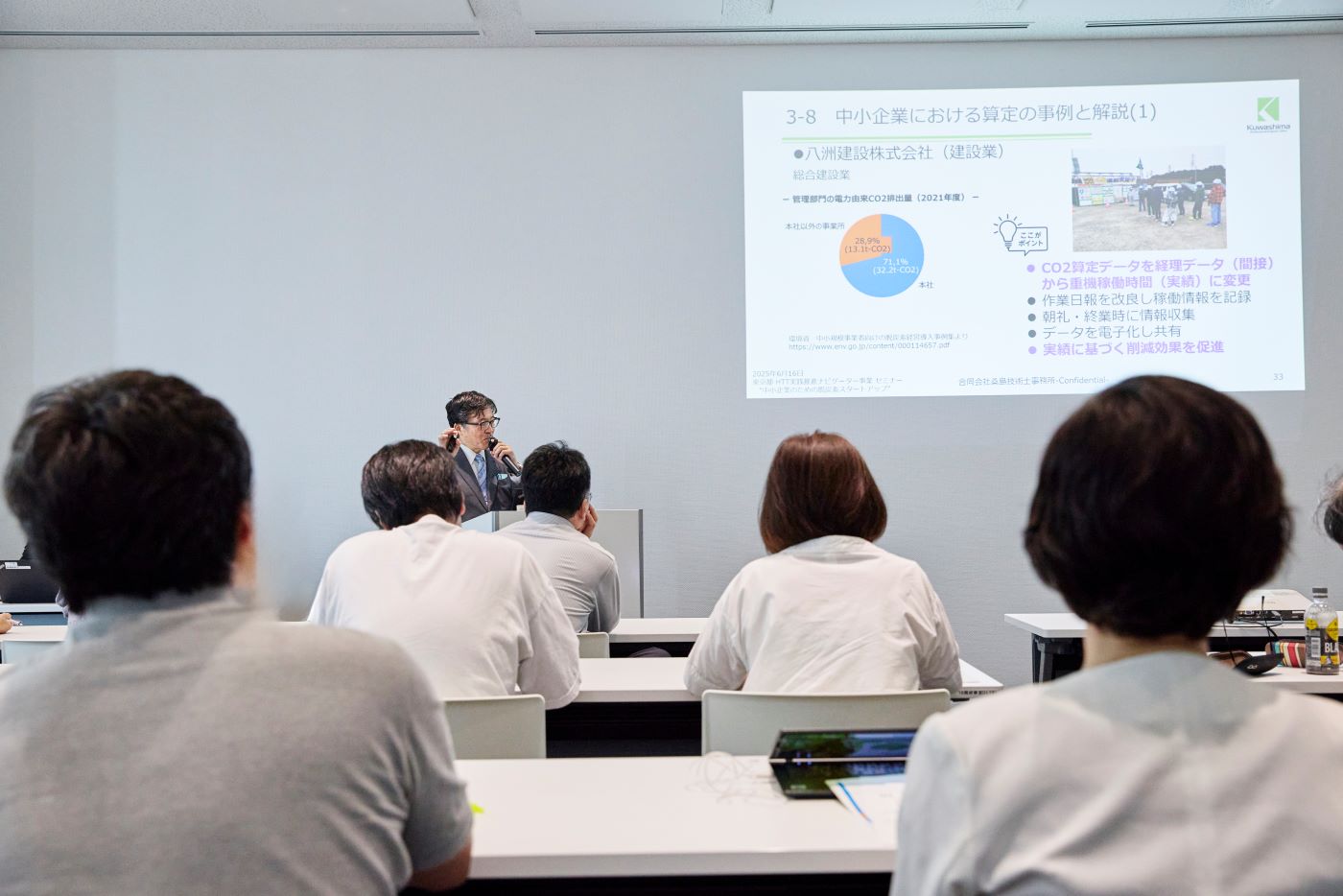
※2 SBTi Science Based Targets initiativeの略。国際NGOの審査により認定を受ける国際的な仕組み。
Q5. 事業拡大で予想される排出量の増加にどう対処するか、目標設定の時点で考えておく必要がありますね。
BAU(ビジネス・アズ・ユージュアル)比、つまり現状維持と脱炭素の対策を行った場合を比較した、目論みをつくる必要があるのだと思います。例えば、事業拡大を続けるなか2050年まで何も対策を講じなかった場合のCO2排出量と、省エネなどでエネルギー効率をあげ、増加が緩やかになった排出量の数値をグラフで表します。それでもゼロにはならない排出量をどうするのかといったときに、新しい技術でこの程度減らして、再エネ導入でこの程度減らして、最後は証書でゼロにします、といった具合に、カーボンニュートラルに至る道筋を示すのです。簡単なことではありませんが、それがあることで取組への本気度を示すことができます。そのためにも、再エネ導入は視野に入れておくべきでしょう。
具体的な取組としては、省エネに向けた設備投資や運用改善、再エネ導入などいろいろな方法がありますが、トピック的に設備投資を行うだけではその先に繋がらないケースが多く、長く続けるには基礎の整理が必要になってくると思います。まずは脱炭素における自社の立ち位置を知り、その先に次の一歩を描くことが大切です。脱炭素経営には「測る」「気付く」「整える」「発信する」この4つの段階がありますが、算定は出発点である「測る」にあたり、その先の気づきが社内体制の整備に繋がると思います。
Q6. 経営と現場のギャップを埋めることが大切というお話もありましたが、社内体制を整えるためのポイントをご教授いただけますか。

経営と現場では日常的に使っている言葉や概念に少しズレがあります。最終的な目的は一緒であるのに、使っている言語ツールや目先の目的の違いで意思の疎通が難しいこともあり、それぞれの考えを翻訳して繋ぐ翻訳者が必要だと考えています。例えば、経営側がエネルギー効率の良い機械設備に更新したいと考えても、現場では機械を24時間フル稼働しており、受注残があるから1年は止められない、という事情があるなど、思いが空回りして事が進まないということが往々にしてあります。そうしたときに、双方の事情を丁寧に伝えて考えを整合していくと、物事がうまく回り出すのですね。ビジネスにおける基本ではありますが、脱炭素を進めるにあたっても非常に大事なことなのです。
また、エネルギー課題というのは全社横断的に協力する必要があり、コストに関わる問題でもありますので、全ての部署と関わりのある経理部門を巻き込んでおくのも大切なポイントです。社内全体で意識を共有するためにも、プロジェクトのロードマップを可視化すると同時に、各部署が何をすべきかナビゲーションする必要もあろうかと思います。このとき大切なのは、担当者が脱炭素に向けた計画を立てる時間を作ってあげること。そこを疎かにすると、担当者が考えるのをやめてしまい、取組が後回しになってしまいます。
Q7. 脱炭素経営をめざす東京都の中小企業の皆さんへのメッセージをお願いします。

2050年のカーボンニュートラルを目指し、東京都は積極的に取組を進めており、中小企業に対しても手厚い支援を展開していると感じています。脱炭素経営というのは、その手厚いサポートをうまく利用して自社の企業価値向上に役立てる絶好の機会でもあります。機を逃さず、脱炭素の波にのって事業を拡大しましょう、ということです。その意識が何より大切です。東京都のさまざまな支援を活用して、脱炭素経営でビジネスチャンスをつかんでいただくことを願っています。
【前のページに戻る】

