脱炭素経営ってどう進めている?

脱炭素経営ってどう進めている?中小企業における取組のリアルとは
株式会社パソナサステナビリティ 代表取締役社長 石田正則氏(左端)
株式会社ヨシザワ 代表取締役 吉澤伸弥氏(左から2番目)
株式会社エニマス 専務取締役 二関智司氏(左から3番目)
株式会社リーテム 総務部部長兼マネジメント推進部部長補 森田建治氏(左から4番目)
経営と脱炭素の両立 中小企業における取組のリアルとは
2025年7月24日、脱炭素経営に取り組む中小企業3社を迎え、「経営と脱炭素の両立 中小企業における取組のリアルとは」と題した、パネルディスカッション形式のオンラインセミナーが開催されました。山あり谷あり、さまざまな課題を乗り越えた企業の現場のリアルをお届けします。
石田氏による基調講演
セミナーのスタートは、パネルディスカッションでファシリテーターを務める株式会社パソナサステナビリティ代表取締役社長石田氏の基調講演から。同社は、人への投資や環境対策とともに、事業成長をめざす企業を支援するサービスを展開。石田氏は「経営課題と環境対策をどのように事業成長に結びつけるのか」と題して、脱炭素経営に取り組む背景にある中小企業の課題について話をされました。

人手不足による倒産件数の増加、物価高に追いつかない賃上げ率の推移、代表者の高齢化による事業成長の鈍化など、さまざまな中小企業の課題が話題となりましたが、直接的に経営を圧迫する要素として挙げられたのがエネルギー価格高騰の問題でした。「ウクライナ情勢によって一気に上がった時期に比べれば落ち着きましたが、原油、石炭、LNG(液化天然ガス)ともに依然として高値が続いています。中長期的にエネルギー市場に影響を及ぼすと想定されますので、中小企業の事業戦略としても5年先、10年先を見越した対策が必要」と、石田氏。燃料価格高騰によるコスト増を価格転嫁できずにいる業種も多く、脱炭素経営でエネルギーコストを削減することは、環境対策である以前に経営戦略でもあると強く感じました。
パネリスト3社様のご紹介
パネルディスカッションに先立ち、まずはパネリスト3社の代表から自社の紹介が行われ、各社より事業概要と脱炭素の取組についてお話いただきました。
■株式会社ヨシザワ 代表取締役 吉澤伸弥氏
「ものづくりのまち」として知られる大田区で1941年に創業。金属切削加工業の町工場で、NC旋盤やマシニングセンターなどの先進機械と熟練工の高品質加工により、多品種の精密部品加工を行っています。パネリストとしてご参加いただいた代表取締役の吉澤伸弥氏は13年前に事業を引き継いだ三代目。補助金や支援制度を積極的に活用して、リーマンショックの煽りで倒産寸前だった事業を立て直しました。工場の水銀灯照明のLED化や営業車をハイブリット車に変えるなど、脱炭素につながる活動にも積極的に取り組み、太陽光による創エネの道も模索中です。

■株式会社エニマス 専務取締役 二関智司氏
神奈川県相模原市で金属部品加工業を営むコバヤシ精密工業株式会社は、脱炭素化を目指す過程で“消費電力を見える化”する装置「エニマス」を開発。「エニマス」により工作機械の消費電力の無駄をなくし、1年間で12万kW、電気代にして約500万円の削減に成功します。「エニマス」を活用したソリューションを新規ビジネスとして展開すべく、2022年、東京都町田市に設立されたのが株式会社エニマスです。「エニマス」は2023年度の日本省エネ大賞「製品・ビジネスモデル部門」をはじめ、省エネや起業に関する数々の賞を受賞。現在は補助金事業のメニューや省エネ診断にも採用されています。

■株式会社リーテム 総務部部長兼マネジメント推進部部長補 森田建治氏
創業100年を超える資源再生事業の老舗企業。先進的リサイクル施設を集めた「東京スーパーエコタウン」に籍を置く東京工場では、回収した使用済みのパソコンや携帯電話、小型家電などから金銀銅などの金属を取り出して再資源化。東京都が進める都市再生プロジェクトの一翼を担っています。東京工場の空調設備に不具合が発生したのを機に、脱炭素化に向けた取組をスタート。照明のLED化や空調設備の更新、建屋の換気・断熱の見直しなどで50%以上の省エネを達成、加えて太陽光発電により創エネも50%を達成し、工場事務所棟のZEB化を実現しました。建物の省エネルギー性能の高さが評価され、2024年には『BELS(ベルス)』認証の最高ランク五つ星も獲得しています。
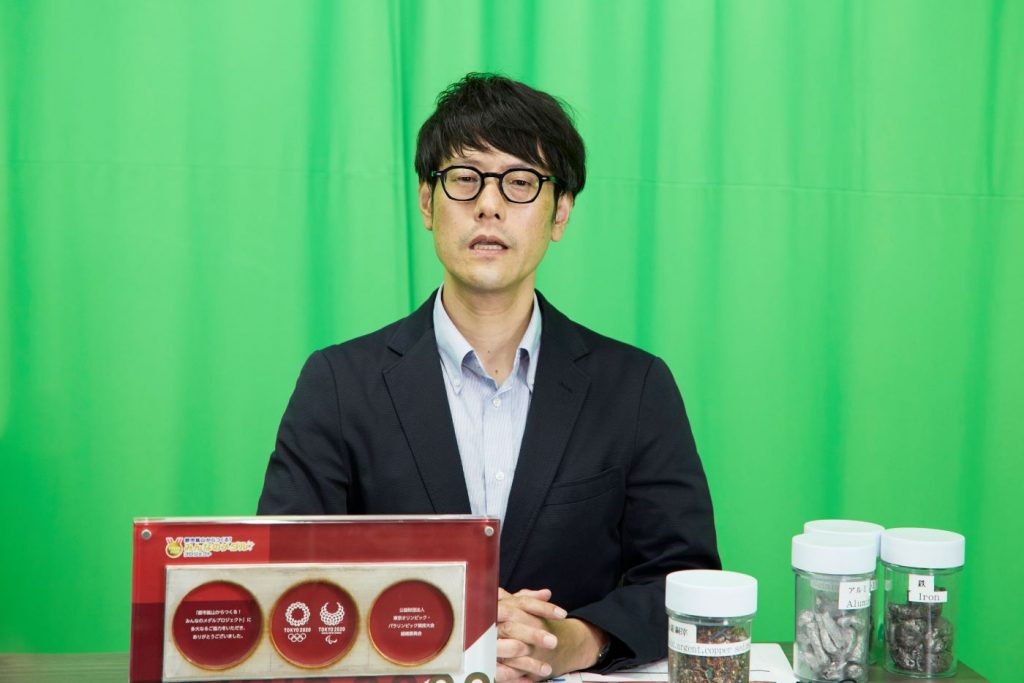
各社の取組について詳しく紹介した記事がありますので、ぜひご覧ください。
・株式会社ヨシザワの記事はこちら
・株式会社エニマスの記事はこちら
・株式会社リーテムの記事はこちら
脱炭素の取組を始めたきっかけ
パネルディスカッションは、以下の4つのテーマに沿って進行しました。ファシリテーターを務める石田氏の気さくな問いかけでパネリストの話題も広がり、テーマを横断した活発な対話が展開しました。
パネルディスカッション4つのテーマ
1. 脱炭素経営のきっかけ、なぜ取組を始めたのか
2. 取組をするにあたっての課題
3. 解決策や結果、今後の目標
4. 取組を検討している企業へのメッセージ
①のテーマ「取組をはじめたきっかけ」でユニークだったのは、株式会社エニマス(以降、エニマス)の二関氏が語る電力測定装置「エニマス」開発の経緯です。昨今の電気代高騰で経営が圧迫され、省エネ補助金を活用して工場の水銀灯をLED化したのがことの始まり。その後すぐに景気が上向いて受注が増え、工作機械を3台新規調達してフル稼働したところ、減らす予定の消費電力が跳ね上がってしまったのだそう。「行政に報告書を提出すると計画と違うと叱られて、本当に悔しかったんです。照明だけの消費電力は下がっているはず。それを証明したくて開発したのが電力測定装置『エニマス』でした」と、二関氏。「エニマス」を商品化して会社を立ち上げたのは前述の通り。ピンチをチャンスに変えて事業成長につなげた、脱炭素経営の好例といえるでしょう。
太陽光発電導入のハードルとは

②取組にあたっての課題、③その解決策、の回答で印象的だったのは、株式会社リーテム(以降、リーテム)のケース。リーテムでは、不具合の出た空調の更新という軽めのきっかけで取組を始めましたが、難易度の高いZEB化まで実現しています。ZEBとはNet Zero Energy Buildingの略※1で、省エネと創エネでビルの消費エネルギーを実質ゼロにすることを意味しますが、創エネで太陽光発電を導入するには屋根の強度が必要なことから、ハードルが高い印象も。リーテムの場合は「工場事務所棟の屋根は、ゆくゆく太陽光を設置する目論みで設計していたようです。ならばこのタイミングで再エネ導入を実現、ZEB化とBELS認証まで進めよう、という計画になりました」と、森田氏は語ります。築年数15年と、比較的に建物が新しかったのも幸いでした。
一方、株式会社ヨシザワ(以降、ヨシザワ)の場合は、太陽光パネル設置による再エネ導入を検討していますが、工場建屋の老朽化で屋根の強度が足りず、いまは導入を諦めざるを得ない状況といいます。ヨシザワに限らず、中小企業の社屋や町工場ではよく耳にする話。窓や壁面にも設置できるペロブスカイト太陽電池や軽量、コンパクト化した太陽光パネルなど、新技術を駆使した装置の普及が待たれるところでしょう。
行政支援サービスの活用が有効
脱炭素の取組については、なにをどこから始めればいいのか見当もつかない、という方も少なくないようです。石田氏は基調講演で「自社だけで考えるには限界があるので、外部の専門家の意見や行政の支援サービスを取り入れることも大切」と語りましたが、パネルディスカッションでは専門家や行政機関の支援の利用について各社に問いかけます。
脱炭素の取組に限らず、経営課題の解決策として、第三者のアドバイスや行政の支援制度をうまく活用しているのがヨシザワのケースでした。第三者の客観的アドバイスを取り入れるメリットについて、吉澤氏はこう語ります。「これまでいろいろな中小企業診断士の先生のお世話になり、他社の社長さんにも相談して『そんなこと聞いてくる社長はいないよ』と驚かれたこともありますが、客観的な意見だからこそ解決の糸口を見つけられたと思っています。中小企業診断士の先生の伴走支援もあって、助成金や公的支援活用の道筋を教えていただきながら、一つひとつ課題解決して歩んだ13年でした。中小企業診断士の多くは大手企業を勤めあげたベテランで、経験も豊富、他社の事例や的確なアドバイスを無料でいただけるのがありがたい。東京都の支援制度には本当に助けていただいています」と、吉澤氏。「中小企業診断士と相談するための事前の準備は?」という石田氏の問いかけには「丸裸でお願いする心」と、吉澤氏らしいお答え。お話からは、公的支援や第三者の視点をうまく取り入れた経営課題解決の道筋が見えてきました。
パネルディスカッションのふりかえり
約1時間にわたるトークセッションでは、パネリスト三者とのリアルな対話により脱炭素経営の多様な取組が見えてきました。ファシリテーターを務めた石田氏はパネルディスカッションをこうふりかえります。

「脱炭素経営については、他社の動向が気になる方も多いことでしょう。今回のパネルディスカッションでは、どのような課題があるのか、行き詰まった時はどうすべきか、どうやったら助言を得られるのかなど、パネリストの生の声から取組を進めるヒントが見えてきたことと思います。それぞれ会社の規模や事業内容は異なりますが、取組を率いるリーダーとしての信念には共通するものがありました。15%しかエネルギー自給率がない国で事業を展開する我々にとって、脱炭素経営は環境対策である以前にエネルギー問題への取組であり、事業成長を左右するコスト削減の道筋であるという考えです。行政は取組を後押しする多様な支援策を用意していますので、まずは公的支援の窓口を訪ねて取組の第一歩を踏み出していただきたいと思います」
公的支援の窓口は多様にあり、どこを訪ねればいいのかわからない、という方も多いかもしれません。HTT実践推進ナビゲーター事業では、経験豊富なナビゲーターが企業ごとに最適な支援策をご案内します。
まずはお気軽にお問合せください。(ご相談は無料です)
【前のページに戻る】

